クリニック継承の注意点~テナント契約~
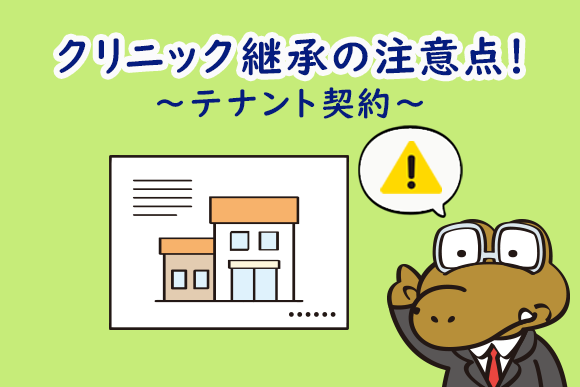
昨今、少子高齢化が進み「後継者問題」は社会問題にまで発展しています。
特に「家業」としてビジネスを営んできた中小企業などは、後継者不在のために廃業を余儀なくされるケースが多く、医療業界も例外ではありません。
そういった中、クリニックの第三者継承は、地域医療存続のための希望の光として注目を集めています。
今回は、『クリニック継承の注意点~テナント契約~』と題して、クリニックを継承する際に注意すべきポイントについて解説してまいります。
クリニック継承でよくある3つのケース
クリニックを第三者継承する際、必ず確認しておかなくてはならないのが「不動産」のことです。
都市部のクリニックの場合、院長先生がご自身で土地や不動産を所有しているケースは珍しく、「テナント開業」が一般的です。
テナント開業の場合は、クリニックを引き継ぐ際に、不動産オーナーに前もって許可を取る必要があります。
以下、テナント開業のクリニック継承でよくある3つのケースをご紹介します。
1.一から契約し直すケース(個人立)
個人立のクリニックの場合、借主当事者が変更となるため、まず最初に継承元の院長先生と不動産所有者との賃貸借契約を解約する必要があります。
その後、改めて賃貸条件の見直しを行い、クリニックを引き継ぐ先生(承継先)が新たに契約を結びます。
賃料や敷金(保証金)などは、継承時の経済的背景や周辺相場などにもよって金額が左右されますので注意しましょう。
2.法人の役員変更のみ行い既存契約を継続するケース(法人立)
クリニックが「個人」ではなく「法人」としてテナントを借りているケースでは、継承後もテナント契約を継続することが可能です。
原則、賃貸条件などはそのまま引き継ぐことになり、継承のタイミングでの敷金・保証金などの返金や積み増しなどはありません。
3.契約者(賃借人)の名義変更のみで、契約条件をそのまま引き継ぐケース
また、1のケースの例外として、継承元のクリニックが個人立の場合でも、名義変更のみで賃貸借契約を継続できる場合があります。
その際には、不動産を所有するオーナーから、敷金及び保証金が返還される場合と、不動産オーナーの手間を削減するために、継承元・承継先・オーナーの三者間で返還請求権を移行する三者間契約を締結するケースがあります。
賃貸借契約書の確認が重要
クリニック継承でよくあるトラブルの事例として、「テナントの引き継ぎは名義変更だけで済む」と勘違いしたまま継承の話を進めてしまい、いざ引き継ぎが始まった際にトラブルに発展してしまったというお話は少なくありません。
事前にテナントの契約について詳しく話をしていない場合、後継者となられる承継先の先生はテナントを一から契約し直すことになるりかねません。
そうなると、敷金・礼金や仲介手数料などが必要となり、当初の開業資金を上回ってしまいます。
最悪の場合は、「継承の話を白紙に戻したい」といった大きなトラブルに発展してしまう可能性もありますので注意が必要です。
長く経営しているクリニックほど、開業時に結んだ賃貸借契約の内容については忘れてしまいがちです。
せっかくまとまりかけた話が白紙となってしまわぬよう、事前に賃貸借契約の内容はチェックし、承継先の先生にお伝えしておきましょう。
この賃貸借契約は複雑な内容になっている場合もあるので、継承にあたり注意が必要な特約事項などがないか、クリニック継承を専門としているコンサルタントへご相談いただくことをお薦めします。
クリニックの継承や閉院などについての個別相談を承っております
いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介したように、テナント契約に関する認識の相違などにより後々のトラブルに発展してしまうといったケースも珍しくありません。
円滑な継承を実現するためにも、クリニック継承を行う際には、事前に必ず賃貸借契約の内容をしっかりご確認いただいてから後継者探しを始めていただくのが良いでしょう。
また、賃貸借契約は複雑な内容になっている場合もございますので、継承にあたり注意が必要な特約事項などがないかについても注意が必要です。
弊社では、引退(親族間継承、第三者継承、閉院準備など)に関する無料の個別相談を承っております。
引退に際しての気掛かりごと等がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。